骨粗しょう症とは
骨粗しょう症は、骨の密度や強度が低下し、骨折しやすくなる病気であり、完全に治癒することは難しいとされています。しかし、適切な治療と生活習慣の改善により、骨密度の維持や骨折リスクの低減が可能です。
治療には、骨吸収を抑制する薬剤や骨形成を促進する薬剤の使用が一般的であり、医師の指導のもとで継続的な管理が重要です。

日本における患者数
2015年における日本の骨粗しょう症の推計患者数は、40歳以上で約1,590万人とされています(男性410万人、女性1,180万人)。
一方、実際に治療を受けている患者数は約135万9,000人(男性8万人、女性127万8,000人)との報告があります。
(日本生活習慣病予防医学協会HPより)
骨粗しょう症は特に高齢女性に多く、60代女性の約5人に1人、80代女性の約2人に1人が罹患しているとされています。
原因
加齢や閉経によるホルモンの変化、カルシウムやビタミンDの不足、運動不足などが主な原因です。
- 加齢
年齢とともに骨を作る能力が低下し、骨密度が減少します。 - 女性ホルモンの減少
女性は閉経後にエストロゲン(女性ホルモン)が急激に減少し、骨密度が低下しやすくなります。 - カルシウム・ビタミンD不足
骨の形成に必要なカルシウムやビタミンDが不足すると、骨が弱くなります。 - 運動不足
運動は骨を強くする重要な要素です。特に、重力のかかる運動(ウォーキングや筋力トレーニング)が重要です。 - 生活習慣の影響
- 喫煙:骨の代謝を悪化させる
- 過度な飲酒:カルシウムの吸収を阻害
- 偏った食事:栄養不足による骨の劣化
- 病気や薬の影響
- 糖尿病、リウマチ、腎疾患などの慢性疾患
- ステロイド薬の長期使用

症状
骨粗しょう症自体には初期症状がほとんどありませんが、進行すると以下のような症状が現れます。
また、骨粗しょう症による骨折の中でも、大腿骨近位部(太ももの付け根)の骨折は深刻で、寝たきりの原因となり、健康寿命を短縮させる可能性があります。
- 骨折しやすくなる(特に背骨、手首、太ももの付け根など)
- 身長が縮む(背骨の圧迫骨折によるもの)
- 背中や腰の痛み
- 猫背(円背)になる

予防・改善策
予防には、若年期からの適切なカルシウムやビタミンDの摂取、定期的な運動習慣の確立が推奨されています。また、定期的な骨密度検査を受け、早期発見と早期治療に努めることが重要です。
1. 食事の工夫

- カルシウムを多く含む食品:牛乳、チーズ、ヨーグルト、小魚、大豆製品
- ビタミンDを含む食品:鮭、いわし、きのこ類
- ビタミンKを含む食品:納豆、緑黄色野菜
2. 適度な運動
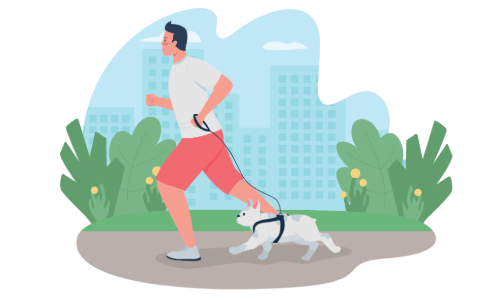
- ウォーキングやジョギング
- スクワットや軽い筋トレ
- ヨガやストレッチ
3. 日光浴
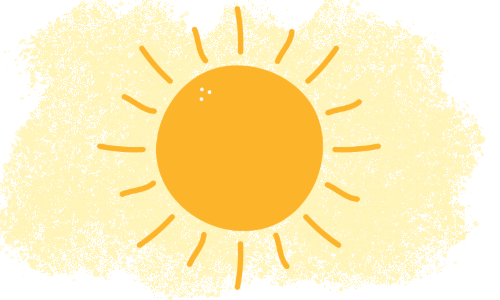
ビタミンDの生成を促進するため、1日15~30分程度、日光を浴びることが推奨されます。
4. 生活習慣の見直し

- 禁煙・節酒
- 規則正しい食生活
- ストレス管理
治療方法
- 薬物療法(例)
- ビスホスホネート製剤(骨の破壊を抑える)
- SERM(選択的エストロゲン受容体調整薬)(女性ホルモンのような働きをする)
- カルシトニン製剤(骨の痛みを和らげる)
- 活性型ビタミンD(カルシウムの吸収を助ける)
- 副甲状腺ホルモン製剤(骨の形成を促進する)
- 生活習慣の改善
食事・運動・日光浴を組み合わせて、骨の健康を維持します。

自己診断
まとめ
骨粗しょう症は「沈黙の病気」とも呼ばれ、気づかないうちに進行します。特に女性や高齢者は注意が必要ですが、適切な食事・運動・生活習慣で予防することができます。早期発見と適切な治療が重要なので、定期的な骨密度検査を受けることをおすすめします。
